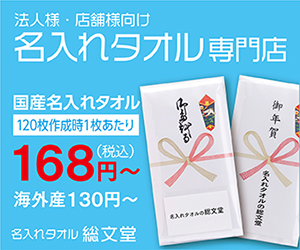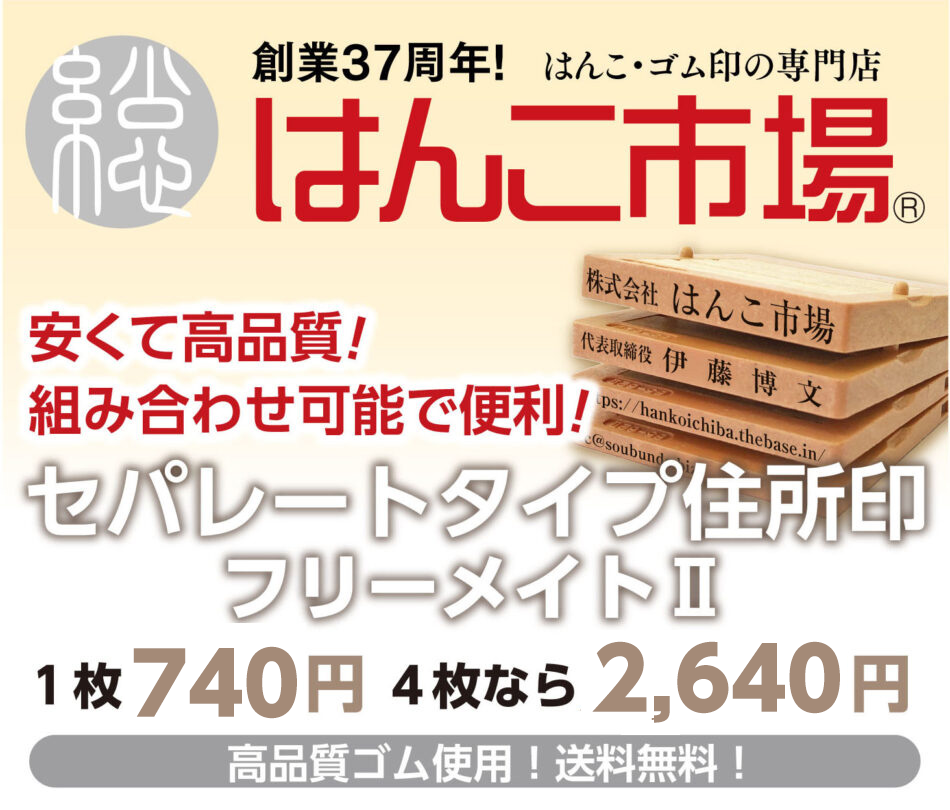波乗り気分でハイキング
- 2014/7/11
- 外房版

梅雨の合間の晴天に恵まれた6月14日、県立東金青年の家主催の『太東岬を歩こう』が行われ、小学生とその保護者13名が参加した。歩くだけではなく、太東岬の歴史と文化を学ぶという趣旨のもと、バスで太東岬付近に移動したあと歩いて飯縄寺(いづなでら)と太東埼(たいとうざき)灯台を見学、海水浴の他、波乗りスポットとしても人気の高い九十九里浜に沿ってハイキングを楽しんだ。
 最初に訪れた飯縄寺(天台宗)は約1200年前に開山。神仏習合の寺で、烏天狗の姿をした大権現が本尊に祀られている。室町時代に建てられた仁王門は鳥が羽を広げたような形の茅葺き屋根。内側の天井付近に、波乗りを楽しむ天狗の彫刻が飾られているのは面白い。コンクリートの門柱、仁王門、本堂への入り口に張られている3つの結界を通り本堂の門をくぐると、天狗のお面が参拝者を見下ろしている。堂内にある結界欄間の彫刻は鴨川生まれの彫刻家、初代『波の伊八』こと武志伊八郎信由(たけしいはちろうのぶよし)の作品。天狗から巻物を伝授される牛若丸の姿、その両側には波と飛龍が彫られている。花鳥風月の彫刻が施されている鐘楼も一見の価値あり。子ども達は願い事を心に念じながら1人ずつ鐘をついた。
最初に訪れた飯縄寺(天台宗)は約1200年前に開山。神仏習合の寺で、烏天狗の姿をした大権現が本尊に祀られている。室町時代に建てられた仁王門は鳥が羽を広げたような形の茅葺き屋根。内側の天井付近に、波乗りを楽しむ天狗の彫刻が飾られているのは面白い。コンクリートの門柱、仁王門、本堂への入り口に張られている3つの結界を通り本堂の門をくぐると、天狗のお面が参拝者を見下ろしている。堂内にある結界欄間の彫刻は鴨川生まれの彫刻家、初代『波の伊八』こと武志伊八郎信由(たけしいはちろうのぶよし)の作品。天狗から巻物を伝授される牛若丸の姿、その両側には波と飛龍が彫られている。花鳥風月の彫刻が施されている鐘楼も一見の価値あり。子ども達は願い事を心に念じながら1人ずつ鐘をついた。
 寺をあとにして、海からの心地よい風を感じながら山間の道を歩くこと15分。『恋のヴィーナス岬』の愛称を持つ太東埼灯台付近の展望台に着いた。太平洋戦争中は海軍技術研究所がありレーダーの実験所がおかれていたが、戦後、米軍によって爆破。そのあと灯台が設置されたが海岸浸食が激しく、昭和47年に内陸へ約100入った現在の場所へ移された。昭和43年までは灯台守がいたが現在はセンサーによって航路を照らしている。『NPO太東埼燈台クラブ』の皆さんの尽力により展望台への道が整備され、年間約10万人が訪れる観光地となっている。気温30度にも関わらず、爽やかな風が吹いていたのは「寒流の影響で潮水が冷やされ、涼しい風をもたらしているから」また、「ここはプランクトンが多く、魚の宝庫。イセエビの水揚げ量は日本一です」と飯縄寺から太東埼灯台までガイドを務めた同クラブ理事長の橋本文江さん。
寺をあとにして、海からの心地よい風を感じながら山間の道を歩くこと15分。『恋のヴィーナス岬』の愛称を持つ太東埼灯台付近の展望台に着いた。太平洋戦争中は海軍技術研究所がありレーダーの実験所がおかれていたが、戦後、米軍によって爆破。そのあと灯台が設置されたが海岸浸食が激しく、昭和47年に内陸へ約100入った現在の場所へ移された。昭和43年までは灯台守がいたが現在はセンサーによって航路を照らしている。『NPO太東埼燈台クラブ』の皆さんの尽力により展望台への道が整備され、年間約10万人が訪れる観光地となっている。気温30度にも関わらず、爽やかな風が吹いていたのは「寒流の影響で潮水が冷やされ、涼しい風をもたらしているから」また、「ここはプランクトンが多く、魚の宝庫。イセエビの水揚げ量は日本一です」と飯縄寺から太東埼灯台までガイドを務めた同クラブ理事長の橋本文江さん。
また少し歩き、九十九里浜沿いの津々ケ浦(つつがうら)で昼食。砕ける荒波に浸食され小さくなりつつある夫婦岩の向こうには、沖へ向かうほどにターコイズブルーが濃くなっていく美しい海が広がっていた。「自然の偉大さに感動した」と小5の男子。
九十九里浜とは旭市の刑部岬からいすみ市の太東岬までの約66キロの弓形の海岸。玉の浦と呼ばれていた時代に源頼朝が距離測定の命を出した。当時の単位は町で1町(ちょう)は109mほど。6町ごとに矢を立てたところ、99本の矢が立ったことから九十九里浜と呼ばれるようになった。河川や海が運んだ土砂が積もってできた沖積平野で、波による浸食により海岸が縮小されつつあるという。
最後のイベントは太東ビーチパークでの水遊び。多くのサーファーを背に、子ども達は打ち寄せる波に大はしゃぎ。カニや貝を拾う子、上半身まで水につかり、びしょ濡れになって戻ってきた子も。帰りのバスの中、最後まで元気だったのは疲れを知らない子ども達だった。