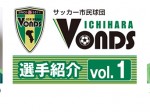- Home
- シティライフ掲載記事, 外房版
- 祝受賞 みんなおいでよ 紙敷塾
祝受賞 みんなおいでよ 紙敷塾
- 2016/7/29
- シティライフ掲載記事, 外房版

山林のほとんどが水源涵養保安林に指定されている自然豊かな大多喜町紙敷地区。昔から日参旗を各戸で順番に回し、地区の神明(しんめい)神社に毎日お参りする習慣があり、民間信仰の集まり千部講、十三日講などが今も続く。住民同士のつながりが強い地域だが、人口259人(平成22年)81世帯のうち、10世帯は一人暮らしの高齢者だ。
『いきいきサロン紙敷塾』のスタートは「みんなが集まる場がなくなると寂しい」という声のあった紙敷老人クラブの解散から。「平成25年、とりあえずやってみようとはじまった」と話すのは代表の君塚良信さん(66)。塾だから毎月19日に集まると決め、試行錯誤をしながら今日まで来た。塾生43名うち60代の若手ボランティアは11名。ボランティアを除いた塾生の平均年齢は80歳だ。
「少子高齢化でさびれていく地域を何とかしたい。塾を心のオアシスにしたい」との思いから、紙敷生活改善センターで開かれる食事会で交流することをメインに血管年齢の若返り、子どもとの交流、バスによる町外学習、郷土史など多岐にわたる講座を開いている。紙敷区より委託を受けて千部講も年4回行う。「昔からある暮らしを生かした新たなコミュニティづくりを目指し、みんながやりたいことを実現する。楽しく集って、少しだけ地域貢献したい」と君塚さん。細かい決まりごとはなく、ボランティアも出来る範囲で手伝うので無理もない。
 取材日も男女40名近くが集まり、千部講のあと昼食を囲んで、漬物の作り方や野菜についておしゃべりしていた。最高齢の91歳の男性は「みんなに会える」と毎月楽しみにしている。紙敷に別荘を持つ船橋在住の夫婦や「楽しいから」と誘われた区外の女性も同席する。70代の女性が「わき腹が締まった」と嬉しそうに話すポールウオーキングは塾の勉強会の賜物だ。いくつものグループがポールを持ち地区を歩いているらしい。午後からは県薬物乱用防止指導員協議会の原田隆一薬剤師による上手な薬の飲み方などの講話だった。
取材日も男女40名近くが集まり、千部講のあと昼食を囲んで、漬物の作り方や野菜についておしゃべりしていた。最高齢の91歳の男性は「みんなに会える」と毎月楽しみにしている。紙敷に別荘を持つ船橋在住の夫婦や「楽しいから」と誘われた区外の女性も同席する。70代の女性が「わき腹が締まった」と嬉しそうに話すポールウオーキングは塾の勉強会の賜物だ。いくつものグループがポールを持ち地区を歩いているらしい。午後からは県薬物乱用防止指導員協議会の原田隆一薬剤師による上手な薬の飲み方などの講話だった。
塾生はただ集まっているだけではない。麻生喜美恵さん、君塚さち子さん、同姓同名の君塚さんの妻さち子さんなどボランティアらは地域活性化に向けた先進的な取り組みをする長野県などにでかけ、研究する。塾には漬物や料理の名人がいるので、それぞれの経験や得意分野を生かし、「地域の特産品のブランド化や食堂開店もしたい」と紙敷の可能性を探っている。
今年1月、紙敷塾は『ちばSSKプロジェクト高齢者支え合い活動奨励賞』を受賞した。『ちばSSKプロジェクト』とは千葉県高齢者孤立化防止活動でSSKは「しない・させない・孤立化」の略。受賞式に出席した麻生さんは「感激し、もっと紙敷をよくしたいと思った」と希望に燃えていた。