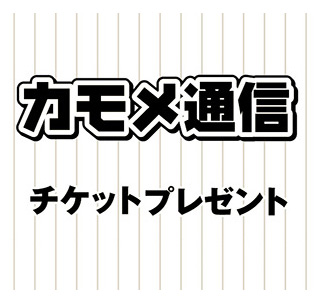- Home
- シティライフ掲載記事, 市原版
- 新しい発見があるかな!?古代市原にタイムスリップ
新しい発見があるかな!?古代市原にタイムスリップ
- 2016/7/8
- シティライフ掲載記事, 市原版

6月12日(日)、市原青少年会館の主催で行われた『新・市原発見!(全5回)』。第1回目は国分寺台周辺を歩き、地理と歴史を自分たちの目で実際に見て、今まで知らなかったことを学んだ。集ったのは国分寺台小、辰巳台東小、白幡小の高学年9名で、すべて女子!「噂の歴女ですね。自分がどの位置にいるのか、地図を見て確認することはとても大切ですよ」と話すのは、講師の鎌田正男さん。
一行が最初に訪れたのは、惣社にある『神門5号墳』。集合した上総国分寺駐車場から歩いて5分ほどの場所にあるその古墳は、約1700年前のもの。円墳と前方後円墳の間の形をしていて、国内でもほとんど見当たらない形だが、こんもりとした丘を眺めて「形をはっきりと空から見たいよ」と子どもから鋭い指摘が飛ぶ一幕も。
次に上総国分寺に戻り、仁王門に祀られている2つの像や薬師堂を見学。普段は前を通るだけの寺にも、数百年の歴史が存在する。60メートルの高さを誇った七重の塔は現存していないものの、土台が残っている。「こうやって、どーんと建っている姿を想像してみて」と野原にある土台を前に鎌田さんが両手を高く突き上げると、子どもたちも一緒に空を見上げたり、土台の写真を撮ったりしていた。
さらに一行は国分寺台団地を抜け、市役所前へ移動。再度地図を見ながら、「国分寺台の台は高台を意味します。今は埋め立てられていますが海では貝や魚をとり、山では木の実やウサギを捕りました。食料が豊富にあったんですね。約5千年前の縄文時代から人が住んでいました」と鎌田さん。現在は多くの学校や施設が建ち、2万人以上が住む町へ発展している。「市民会館は合唱コンクールで何回も来たよ」と近くの施設に目を走らせながら、祇園原貝塚を通り、最終地点の上総国分尼寺へ。
 「上総国分寺は僧侶、上総国分尼寺は尼寺として1250年ほど前に建立されました。武士の争いによる火災で燃えてしまったので、今あるのは復元したものです」と尼寺内、展示館担当者。館内の復元模型を眺めて広大な敷地内にあった建物に想像を膨らませたあと、外の復元された中門を含めた史跡を見学する。108本の柱は緻密にデザインされ、雨に濡れやすい場所は材質を変えるなど、「どうしてそんなことが昔の人に分かったの?」と思えることばかり。「時々、初めて聞く言葉があって難しかったけれど勉強になった。夏休みの自由研究に使えるかも」と子どもたちはそれぞれの感想を話す。
「上総国分寺は僧侶、上総国分尼寺は尼寺として1250年ほど前に建立されました。武士の争いによる火災で燃えてしまったので、今あるのは復元したものです」と尼寺内、展示館担当者。館内の復元模型を眺めて広大な敷地内にあった建物に想像を膨らませたあと、外の復元された中門を含めた史跡を見学する。108本の柱は緻密にデザインされ、雨に濡れやすい場所は材質を変えるなど、「どうしてそんなことが昔の人に分かったの?」と思えることばかり。「時々、初めて聞く言葉があって難しかったけれど勉強になった。夏休みの自由研究に使えるかも」と子どもたちはそれぞれの感想を話す。
自分なりの市原が、発見できたかな?同講座は今後、五井海岸の海づり公園や姉崎神社、あずの里など古代から続く市原の特色ある場所を訪れる予定。対象は小4から高校生まで。参加希望等、詳細は問合せを。
問合せ 市原青少年会館
TEL 0436・43・3651