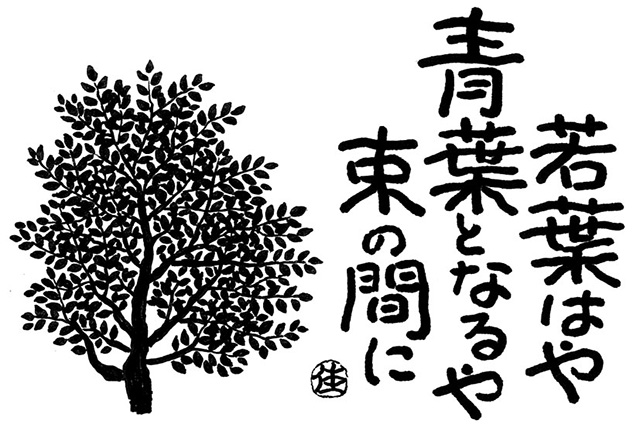- Home
- シティライフ掲載記事, 市原版
- 縄文時代の人ってどんなことをしていたの
縄文時代の人ってどんなことをしていたの
- 2018/7/6
- シティライフ掲載記事, 市原版

6月2、3日にかけて袖ケ浦市郷土博物館で開催された『第23回ミュージアムフェスティバル~ドキドキ!縄文まつり!』。取材日の2日、会場には多くの親子連れが訪れ賑わっていた。同館館長の井口崇さんは、「今年2月より国史跡指定記念で開催していた特別展『山野貝塚のヒミツを探る』の展示最後の週末と合わせ、双方を楽しんでいただけると思います。例年3千人ほどご来場いただきます。イベント内容は例年と同じものもありますが、今年は特に縄文時代の貝塚に合うものを揃えました」と話した。
気温30度近くになるこの日、博物館正面入り口で汗をかきながら素早く上下に手を動かしているのは『火おこし体験』。はずみ車を使って回転力を高める舞ぎり方法で火おこしに挑む子ども達。同館近辺出身という女性は、真剣に火おこしをする小学校5年生の娘さんを眺めながら、「偶然実家に帰省していて公園に遊びに来たらイベントを発見して、娘が真っ先に行きたいと。ちょうど学校で歴史の授業が始まったので興味が湧いたんだと思います。良い体験でした」と楽しそうに、その姿を写真に収めた。
また、常に子ども達が途絶えない様子だったのは今年一押しの『貝輪づくり』。遺跡から様々なアクセサリーが見つかっているが、その用途は現在と似ている。ヘアピンや耳飾り、首輪や足輪などがあり、それら貝からできたものを貝輪と呼んでいる。
山野貝塚の特別展ではアカニシやオオツタノハ、イタボガキでできた貝輪が展示されているが、同イベントではベンケイガイとホタテを使用した。固く丈夫で力が必要なベンケイガイと貝が大きく薄いので穴は開けやすいが、少し壊れやすいホタテ。ハンマーで貝の中心を叩き好きな大きさの穴を開け、水ですすぎサンドペーパーで研磨する。首から貝輪をぶらさげた母子はもちろん、「可愛い!」のひとこと。
外のテントの下、夢中でハンマーを使って石を叩く男児を発見。彼が体験していたのは『化石発掘』。栃木県那須塩原から収集した化石に、ドライバーを当ててハンマーで数回叩くと、化石が埋まっている箇所で割れるという。「これは30万年前の植物です。色など違うのが分かるかな?」とスタッフの女性に促され、手元の化石とファイルの中の写真を何度も見比べていた。
同イベントでは、他にもまが玉作りやあんぎん織体験など多くを開催。ちょっと特別な『平安貴族体験』では、市内在住の女児(4)が十二単を試着。訪れた祖母が愛らしさに目を細める中、本人も終始はにかんだ笑顔を浮かべていた。普段、ちょっと敷居の高いイメージの博物館。親子でより身近な存在に感じられたのではないだろうか。