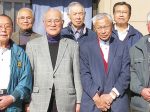- Home
- シティライフ掲載記事, 市原版
- 日本人の侍魂に火を付ける!? 立身流を見よ
日本人の侍魂に火を付ける!? 立身流を見よ
- 2018/10/12
- シティライフ掲載記事, 市原版

次世代に残したいと思う『ちば文化資産』、及び千葉県指定無形文化財の1つに定められている古武術『立身流』。剣術と居合術を中心に柔術や槍術、長刀や棒などを扱う総合武術である。「かつては福沢諭吉も晩年まで稽古を続けていたと伝記に書かれています。剣道のように激しく打ち合うのではなく、居合武道のように型を綺麗に見せるだけとも異なります。イベントでは真剣を使って実際に竹や藁の束を斬るんですが、みなさん息をのんで驚いてくれます」と話すのは、立身流市原支部長の近藤恭弘さん。自身は20年以上の経験者で、現在6名ほどの市原支部の発展に尽力を注いでいる。
 立身流は、室町時代の永正年間に愛媛県の伊予の国で生まれ、江戸時代に入ると下総国佐倉藩(現、千葉県佐倉市)の藩主、堀田家において藩外不出の武術の中枢とされるようになった。伝書や古文書とともに伝承されている立身流は、第22代目宗家である加藤紘さんの佐倉本部を中心に、市原支部、八街支部、福島県の郡山支部、東京都大田区の矢口支部などで活動を続けている。
立身流は、室町時代の永正年間に愛媛県の伊予の国で生まれ、江戸時代に入ると下総国佐倉藩(現、千葉県佐倉市)の藩主、堀田家において藩外不出の武術の中枢とされるようになった。伝書や古文書とともに伝承されている立身流は、第22代目宗家である加藤紘さんの佐倉本部を中心に、市原支部、八街支部、福島県の郡山支部、東京都大田区の矢口支部などで活動を続けている。
「伝承される古文書や巻物に書かれた技はとても多く難しいです。でも免許皆伝されると巻物がもらえ、人生の目標にもなります。30年、40年続けていく世界なので、たとえ週1回しか練習できないとしても細く長く続けてもらえたら嬉しいです」と近藤さんは続ける。
 城下町ではなかった市原市にとって、古武術はなじみの薄いものなのかもしれない。しかし、腰に刀を身に付けて堂々と立つ風格は勇ましく、声を上げて相手に立ち向かう姿は圧巻。かつての武士を連想させる迫力は、男性だけでなく女性や子どもまでも虜にすることだろう。
城下町ではなかった市原市にとって、古武術はなじみの薄いものなのかもしれない。しかし、腰に刀を身に付けて堂々と立つ風格は勇ましく、声を上げて相手に立ち向かう姿は圧巻。かつての武士を連想させる迫力は、男性だけでなく女性や子どもまでも虜にすることだろう。
「大変な体力が必要なわけではなく、女性も大歓迎です。大学生の女の子が1人いて、6年前はすこし猫背だったけれど今では背筋が伸び佇まいも綺麗になりました」と近藤さん。市原支部は、10月14日(日)に開催される『大多喜お城まつり』で演武を披露する。出演は10時45分から11時15分を予定しており、当日は剣術や長刀、真剣での試し斬りなどを行う。300人の武者行列と共に披露される立身流は会場を大いに盛り上げることだろう。
また、練習は毎週3回行われているが、1日からでも参加可能。月曜日に若葉中、水曜日に五井中、金曜日に千種中で、いずれも時間は19時から21時まで。初年度のみ入会金として年1万円、その後年会費3千円。参加方法、および詳細は問合せを。
問合せ 近藤さん
TEL 080・6614・6508