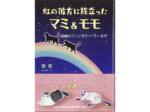埴輪生産の背景を考える
- 2014/1/17
- 市原版

埴輪生産の背景を考える
昨年12月、埋蔵文化財調査センターで講座『埴輪のひみつ』が開かれ、6世紀末の前方後円墳、山倉1号墳(西広)で出土した埴輪の生産体制についての研究成果が披露された。講師は学芸員の小橋健司さん。
各埴輪には特徴がある。例えば原材料となる胎土の成分や円筒埴輪に施されているハケメ、人物埴輪の装着物の形状など。ハケメとは薄い板状の木でつけた筋状の擦痕のこと。これらを分析した結果、山倉1号墳の埴輪は埼玉県生出塚遺跡窯で焼成されたという説が有力に。また、各個体がほぼ同じ製作技法であるにも関わらず、円筒埴輪の口縁部の違いなどは作り手のクセによるもので、そのパターン数は最少でも13人の工人が存在していたことを示している。
約80キロ離れた場所まで300弱の埴輪を運んだ手段は水上交通だったと考えられている。「生出塚で生産された埴輪が現市原市に運ばれたと推測されている同時期に、上総から石室用材として磯石が埼玉古墳群まで運ばれており、古墳築造プロジェクト同士の関係を読み解く鍵にもなるのではないか」と小橋さん。
聴講者数は68名と超満員。熱心に耳を傾ける姿が見られ、講座終了後も多くの質問が飛び交っていた。
Warning: Attempt to read property "show_author" on bool in /home/clshop/cl-shop.com/public_html/wp-content/themes/opinion_190122/single.php on line 84