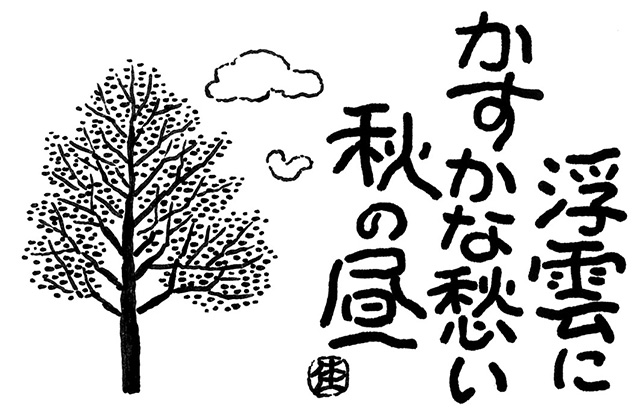郷土の習俗を伝える技 県指定伝統的工芸品『角凧・袖凧』
- 2013/2/8
- 市原版

郷土の習俗を伝える技
千葉県指定伝統的工芸品『角凧・袖凧』製作者 金 谷 司 仁 さん
日本各地の風土、習俗に溶け込み、その土地ならではの形や絵柄となって残る和凧。『てんばた』(宮城)、『いかのぼり』(大阪)、『はた』(長崎)など凧を表わす言葉も揚げる季節も地方によって異なる。漁師が大漁を祝って着た色鮮やかな長半纏『万祝』を模した『袖凧』の発祥の地は千葉県。ほかにも県外から伝わり、変化したさまざまな郷土凧がある。
上総では男の子が生まれると健やかな成長を願って祖父母や親戚が子の名前や家紋を入れた大凧をお祝いに贈るという。かつては5月5日前後、風向きのよい日を選んで米俵3俵に糸を括りつけた凧を大空に揚げ、その下で親戚縁者が集い祝宴を開いた。凧の大きさは畳3枚から6枚分ほど。千葉県指定伝統的工芸品の郷土玩具『角凧・袖凧』の製作者、金谷司仁さん(77)は「縁起物だから必ず揚がるように作る」と職人の心意気を語った。凧の骨はねばりのある大名竹、和紙はじょうぶな西の内製を使う。「提灯屋だったから文字は得意。家紋は50種類ぐらい頭に入っている」。絵を描くときは滝登りをする鯉と金太郎を描いた『鯉金』、大漁を知らせる文をくわえる『文鶴』が多い。絵の具は外光に透ける染料。びゅんびゅんと勇壮な音を出す『うなり』に昔はくじらのひげを使ったという。親子2代にわたり注文を受けることもある金谷さん。作り手として招かれる盛大な酒宴より印象に残っていることがある。ある時、凧が空を舞わなかったのだ。その日は宴会だけすませ、別の日に作り直して揚げたがうまくいかなかった。ようやく3度目に成功したのが「今でも忘れられない」という。宴会のお土産は決まって柏餅だった。
浅草で提灯作りの修行をした祖父作蔵さんが明治38年に市原市で際物店を開いたのが凧屋のはじまり。シーズン間際に必要なものを売ることから際物店と呼ばれ、正月飾り、雛人形、鯉のぼり、盆飾りなどを扱った。「凧を手掛けるようになったのは提灯を作る竹と紙を使い、筆で文字を描いたからではないか」と3代目の金谷さんは話した。歳時物に囲まれた暮らしのなかで自然に物づくりを覚えた。出征した人の無事を祈る絵馬を作ったのは戦中と終戦後数年間。電気は通っていたものの、夜間の外出に懐中電灯がわりに提灯が使われていた昭和20年代、金谷さんは自転車で近くの村を回り、提灯修理を請け負ったという。花輪も作っていたことから昭和43年に葬儀社を起こしたのは父政吉さん。金谷さんは定年退職するまで市内の福祉施設に勤め、家業を手伝いながら父親に凧作りを教わった。「竹割りを失敗しては怒られた」そうだ。
10年ほど前、金谷さんが会長を務めたこともある市原市凧保存愛好会の会員が凧の作り方を設計図付きでまとめてくれた。「自分は作るだけだから」と喜び大切に保存している。今年1月、大正時代から家に伝わる凧の下絵を簡単な冊子にした。「真似されるのではと心配する人もいるが趣味で楽しむ人の参考にしてもらいたい。凧屋で身は立てられないから」と図柄の伝播にこだわらない。百貨店や博物館の伝統工芸展に出品するけれども「知人に会うと気恥ずかしいから会場での実演制作はやらない」と柔和な顔で笑った。最近は贈り物や装飾品として作るのがほとんど。終戦直後は小ぶりな凧をいくつも作っておくと子どもたちが買いにきた。金谷さん自身も少年の頃「特別うまくなかったけれど揚げた」そうだ。今も小学校で凧工作を教えると喜んでもらえる。「でも海岸や空き地もなくなり、凧揚げは子どもの日常の遊びではなくなった」と寂しそうに話した。
出羽三山信仰の『梵天供養』、毎年8月15日に行われる『椎津のカラダミ』(県指定無形民俗文化財)など地域の伝統行事に使う万燈も祖父の代から作ってきた。万燈とは紙花で飾った細長い竹をつけたバレンをあしらった華やかな山車のこと。源平合戦、天の岩戸などをテーマにした人形を配し、高さ15メートル以上になるものもある。「組み立てるだけで1週間以上かかる」。万燈や行事にまつわる話を聞きたいと郷土史研究家などが訪ねてくるほど金谷さんの仕事は地域の習俗に欠かせない。
平成23年、長男の政司さん(48)が作る『角凧・袖凧』も伝統的工芸品として県の指定を受けた。「嬉しいが息子にはまだ教えることがある」と伝統技術には厳しい。登録名に地名をいれないのは「角凧は江戸、袖凧は上総の凧と決まっているから」と自負を見せる。
Warning: Attempt to read property "show_author" on bool in /home/clshop/cl-shop.com/public_html/wp-content/themes/opinion_190122/single.php on line 84