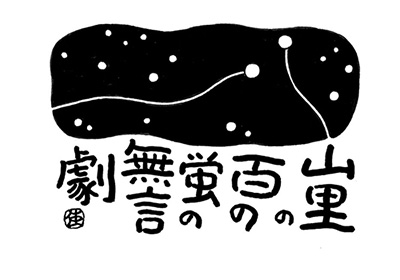- Home
- シティライフ掲載記事, 市原版
- ふるさとビジター館
ふるさとビジター館
- 2016/11/18
- シティライフ掲載記事, 市原版
- ふるさとビジター館

マツナ絶滅の憂慮
空気の冷たさを感じ、周囲が秋の色に染まりはじめる時期、養老川河口の岸辺では、たくさんの星型の実をつけるマツナを見ることができます。
 マツナは、関東以西、四国、九州に分布し、海岸や河川の河口域などの塩分が多く含まれる砂地などに生育する1年草。葉が松の葉にとても似ていることからその名がつけられたそうです。草丈は約40~100センチ、茎からは多くの枝を出し、8~10月頃に淡黄色の小さな花をつけます。若芽時のマツナの葉は、線形で透明感あふれる緑色をしており、どことなく上品で優美な感じがしますが、秋には茎が木質化して堅くなり、荒々しい感じになります。
マツナは、関東以西、四国、九州に分布し、海岸や河川の河口域などの塩分が多く含まれる砂地などに生育する1年草。葉が松の葉にとても似ていることからその名がつけられたそうです。草丈は約40~100センチ、茎からは多くの枝を出し、8~10月頃に淡黄色の小さな花をつけます。若芽時のマツナの葉は、線形で透明感あふれる緑色をしており、どことなく上品で優美な感じがしますが、秋には茎が木質化して堅くなり、荒々しい感じになります。
マツナの種は、風や水に流されて散布されることから、発芽する場所(生育環境)は、種親の周辺や大潮時の満潮線付近となっています。このような場所は、流木や漂着ゴミが堆積していることが多く、種の上にゴミ等があると発芽しにくいこと、また、大雨による川の増水により定着した種が流されやすいことなどから不安定な生育環境となっています。 マツナは、千葉県レッドデータブックでは重要保護生物Bに指定されています。千葉県内におけるマツナの生育地は、東京湾内湾の数箇所に限られ、そのうちの1箇所が養老川の河口域にあります。
マツナは、千葉県レッドデータブックでは重要保護生物Bに指定されています。千葉県内におけるマツナの生育地は、東京湾内湾の数箇所に限られ、そのうちの1箇所が養老川の河口域にあります。
8年前に養老川河口域の生育数を確認した時は、数百本あり、広範囲に生育していました。しかし、とても残念なことに、今や生育箇所は局所的で数本程度となっています。その原因は、自然的要因、人為的要因の両方と思われます。市原市の生育種の絶滅が憂慮される状況です。
(ナチュラリストネット/時田良洋)