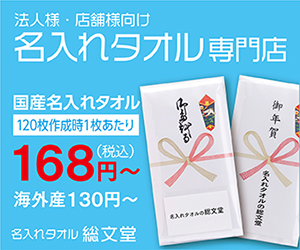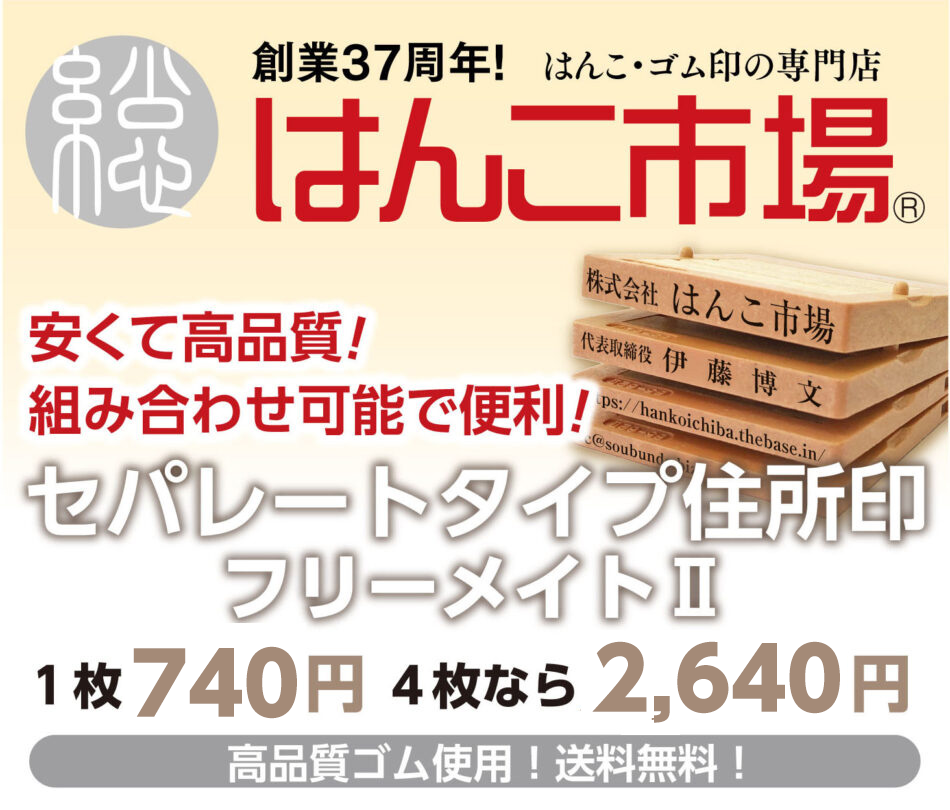- Home
- 外房版, シティライフ掲載記事
- 学びの旅で人生が変わる 世界遺産の旅「長崎・天草地方の潜伏キリシタン関連遺産群の旅」【市原市】
学びの旅で人生が変わる 世界遺産の旅「長崎・天草地方の潜伏キリシタン関連遺産群の旅」【市原市】
- 2021/9/2
- 外房版, シティライフ掲載記事
- 外房, 市原市

6月12日(土)、黒田尚嗣さん(65)(ペンネーム『平成芭蕉』)の講演『世界遺産の旅~長崎、天草地方の潜伏キリシタン関連遺産群の旅』が開催された。コロナ禍のため、主催の市原市国際交流協会からの配信で、ZOOMによる個別視聴と五井公民館でのパブリックビューイング(人数制限あり)での実施。日本旅行作家協会会員でクラブツーリズム(株)顧問でもある黒田さんは「忙しい現代社会ですが、世界の歴史や文化を学んで好奇心をかき立て、ゆっくり旅をすると、ときめきや共感が得られます。学びの旅で味わったワクワク感はその後の人生を変えるのです。人生百歳時代を楽しく健康的に生きましょう」と語る。
潜伏キリシタンとは?

ダイヤモンド・プリンセス号にて旅中の黒田さん
弾圧と鎖国の影響で宣教師不在の中、潜伏キリシタンたちは、日本の民話、伝承、神話などを取り入れて独自のキリシタン信仰文化を築いていった。天草の崎津集落では神社の境内で「あんめんりうす」とオラショ(祈りの言葉)を唱えたり、漁業の神の「えびす」像をデウスとして崇拝したり、アワビの貝殻の内側の模様を聖母マリアになぞらえたりしてオリジナルな祈りを継続。平戸の春日集落では、家屋の奥まった納戸に納戸神と呼ばれるご神体を祀って、古来信仰してきた安満岳とあわせて崇敬。一言で潜伏キリシタンと言っても、実は地域ごとに特色があるのだそうだ。
やがてキリスト教が解禁となると、各地の潜伏キリシタンは晴れてクリスチャンに。しかし中には、祖先を敬う日本的な習慣を大事にし、仏壇や神棚を焼き捨てることのできない人々もいた。彼らはクリスチャンにはならず、それまで自分達が育んできた日本的なキリスト教を継続して信仰した。このような人々を潜伏キリシタンと区別して『かくれキリシタン』と称するとのこと。長崎の世界遺産の旅に出かける前に、潜伏キリシタン・かくれキリシタンを区別してしっかり理解しておくことが欠かせない。
登録の経緯からわかること

奈留島の江上天主堂
「弾圧から逃れて外海へ、五島列島へ、黒島へと移動し僻地を開拓していった潜伏キリシタンの足跡によって、外国のものを日本風に取り入れ、自然と融合させる日本人の生き方を知ることができるのです。天国か地獄か、YESかNOかのヨーロッパと違い、日本民族は異質のものを混ぜ合わせながらグレーにして取り込むことができるのですね」と黒田さん。
長崎の学びの旅が拓く明日

大浦天主堂
旅する前にしっかり学んで、自ら疑問を持ち、調べて初めてわかることがある。日常でも何気なく見ているものの奥に、多くのことが隠れているものだが、それは旅も同じ。「LOOK(ちらっと見る)からWATCH & SEE(観察と理解)への転換」を黒田さんは推奨する。長崎の学びの旅で潜伏キリシタンを理解し、日本文化の底流を体感すること、それは日本人である自分自身を世界の視点で捉えることに繋がっていくのだろう。
・黒田尚嗣さんHP 旅のコンセプト
http:heiseibasho.com
問合せ:市原市国際交流協会の入会やボランティアについて
mail:iia_ichihara@ybb.ne.jp