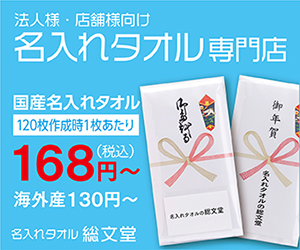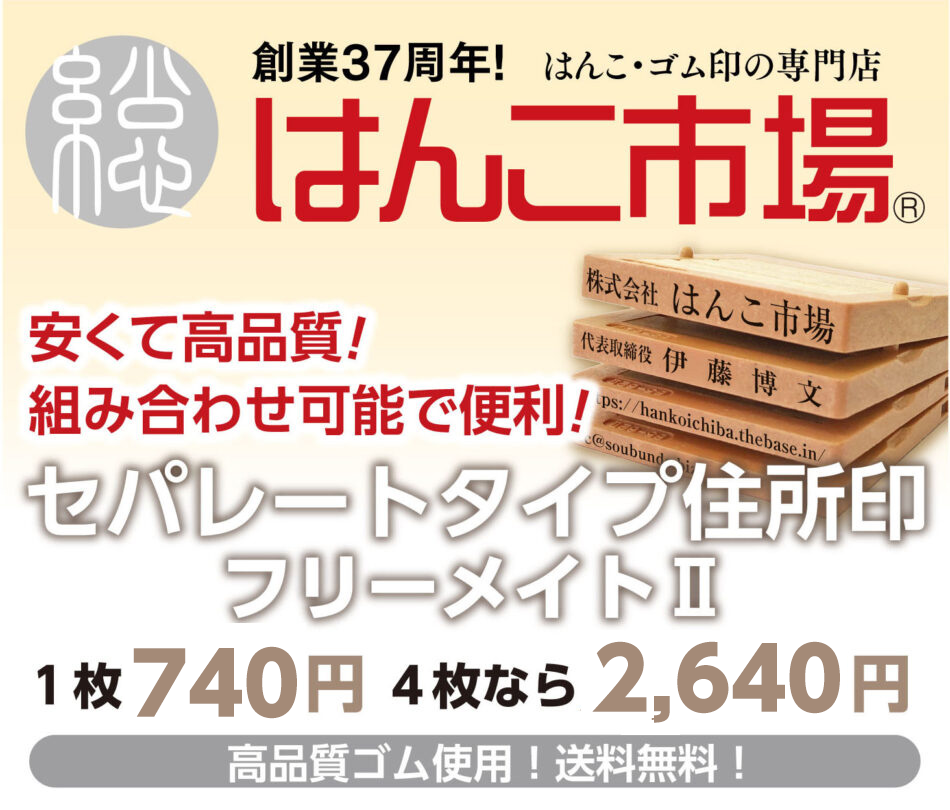- Home
- 市原版, シティライフ掲載記事
- 中近世の甲冑と戦
中近世の甲冑と戦
- 2015/11/27
- 市原版, シティライフ掲載記事

千葉県立中央博物館大多喜城分館で、企画展『甲冑とその時代~甲冑の様式を中心に~』が12月6日まで開かれている。平安時代後期から江戸時代まで、迫力満点の兜と鎧が時代順に陳列されており、戦事情に左右された形態の変遷をたどることができる。
平安から室町時代までの大鎧は、牛皮や鉄製の札と呼ばれる長方形の小片を少しずつずらして重ねたものを横に並べ、糸や犬の皮でできた紐で綴じ合わせて作られていた。小片は漆塗りで、鎧1領につき約1500枚から1800枚。
 36キロもある国宝の『赤糸威大鎧』(複製)など騎乗したまま戦うことを想定した様式から、南北朝時代以降は徒立戦で動きやすい様式へと移行。戦国時代から江戸時代にかけては鉄砲など新兵器の登場により、胸板は黒の漆塗りに紺の糸を施した板札が主流。籠手や臑当まで完全装備の具足が普及していった。
36キロもある国宝の『赤糸威大鎧』(複製)など騎乗したまま戦うことを想定した様式から、南北朝時代以降は徒立戦で動きやすい様式へと移行。戦国時代から江戸時代にかけては鉄砲など新兵器の登場により、胸板は黒の漆塗りに紺の糸を施した板札が主流。籠手や臑当まで完全装備の具足が普及していった。
来場者に人気が高いのが、桃山時代から江戸時代のものと推測される『紅糸中黒糸威丸胴具足』。同具足の兜『鉄十六枚張阿古陀形筋兜』には全体に青貝螺鈿が施されており、鎧の胴下部分、草摺り裾板には桐紋が見られる。兜には「春田定光作」の銘があり、鎧は徳川家の甲冑制作に深く関与した岩井与左衛門一派の仕事と強い共通性が見られる。
豊臣秀次所用といわれる甲冑に、お子様も楽しめる変わり兜。全国で初公開の資料もあり、見ごたえたっぷりのラインナップだ。甲冑の変遷を観察し、中世の戦模様に思いを馳せてみては。
月曜休み。9~16時30分(入館16時まで)。入場料は一般300円。
問合せ 大多喜城分館
TEL 0470・82・3007