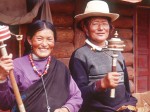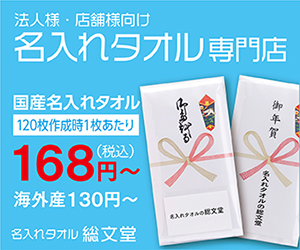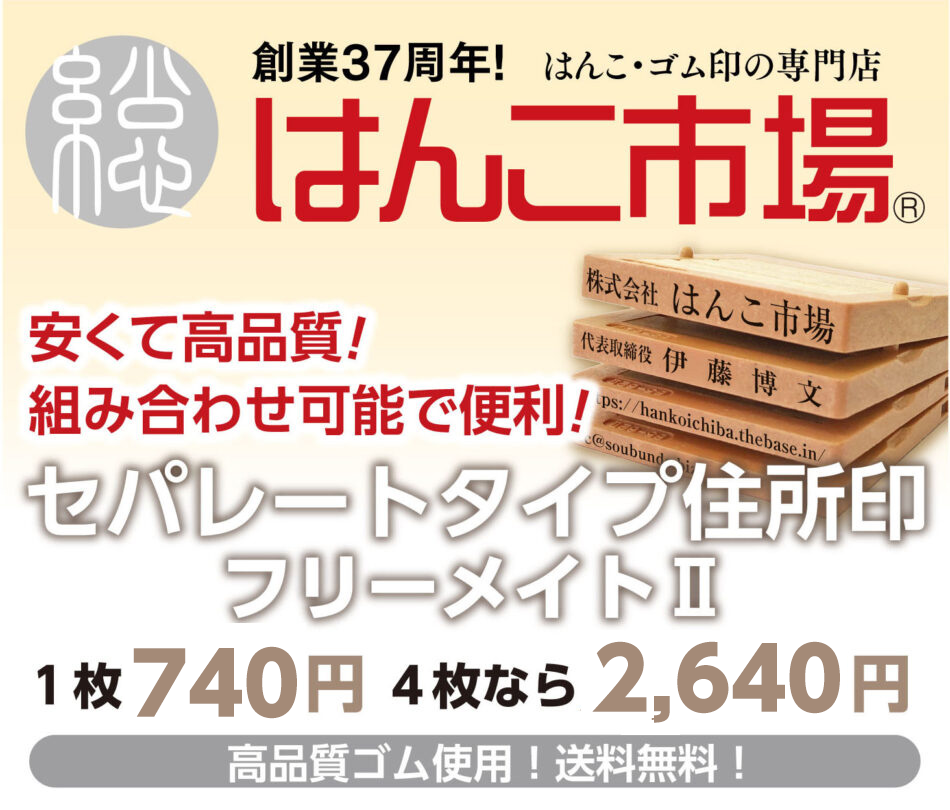- Home
- 市原版, シティライフ掲載記事
- 房総往来
房総往来
- 2018/6/8
- 市原版, シティライフ掲載記事

没後200年、その足跡
山里吾郎
うっとうしい梅雨の季節になると、俄かに活気づく町がある。水郷あやめで知られる佐原。しかも今年は町が生んだ偉人、伊能忠敬の没後200年にあたる。50歳を過ぎてからの全国踏破、正確な日本全図を生み出した大偉業。いつもの町会ハイキング部と一緒に、その足跡をたどった▼佐原駅に到着したのは午前9時過ぎ、駅前に建立された伊能忠敬像が真っ先に飛び込んできた。新聞報道によれば、5月20日に除幕されたばかり。筆や測量野帳を手に、方位確認の目印にしたと言われる北極星方向を指差す翁の旅装姿がいかにもリアルだ▼周遊バスを利用してまずは小野川沿いへ。小江戸の風情を残すしっとりとした町並みを楽しみながら早速、「伊能忠敬記念館」を訪れた▼1745年、現在の九十九里町で生まれた忠敬は17歳で佐原の伊能家に婿養子、名主や村方後見として活躍。隠居後、50歳で江戸に出て天文方・高橋至時に入門。師の勧めもあり55歳の時に東北・北海道の測量に旅立つ。これを皮切りに71歳まで10回に渡って全国を測量した。第4次測量までは費用の大半を忠敬が負担、随行も少なく艱難辛苦を極めた。しかし地図の正確さはやがて幕府を動かし、後半は国の事業として進められたという▼測量の度に地図化していき日本全図が完成したのは1821年。忠敬が73歳で没してから3年後で、地図作りは同行した弟子によって続けられた▼全て手書き。印刷技術もない時代、1枚の元図からどうして複数の地図が残せたのか?「紙を重ねて針を刺したんですよ」-係員の説明でそんな疑問も解消した。