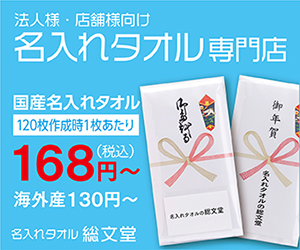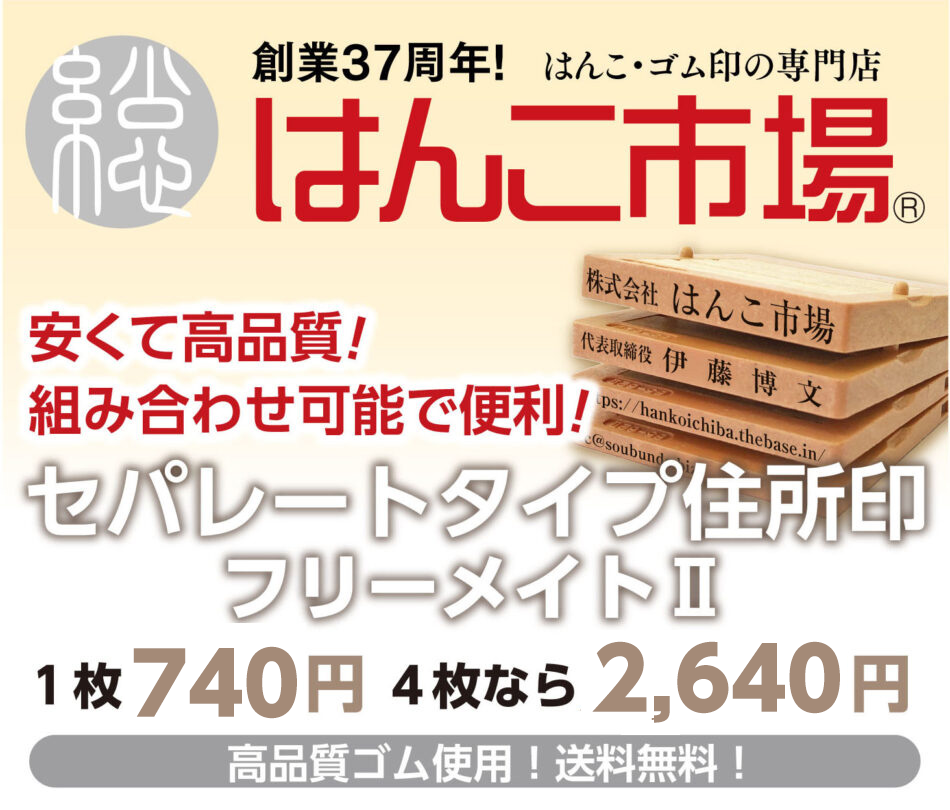- Home
- 外房版, 市原版, シティライフ掲載記事
- 昭和のモダニズム建築を次世代につなぐ ~大多喜町役場庁舎~【大多喜町】
昭和のモダニズム建築を次世代につなぐ ~大多喜町役場庁舎~【大多喜町】
- 2022/2/24
- 外房版, 市原版, シティライフ掲載記事
- 外房

大多喜町役場庁舎は昭和34年(1959年)建設の中庁舎(なかちょうしゃ)と、平成23年(2011年)に新築された本庁舎からなり、新旧の建物が調和し隣り合う。中庁舎は鉄筋コンクリート造のモダニズム建築ながら、城下町の風景に溶け込み、温かみのある存在感を示している。設計は早稲田大学建築学科で教鞭をとった建築家・今井兼次で、千葉県では初となる日本建築学会賞を受賞した。
今井氏は大多喜町を「関東の大和」と称え、土地の歴史や自然をテーマに建物の随所に様々な工芸技法を盛り込んだ。それらを鑑賞するのはまるで宝探しをするかのようだ。

大会議室の天井
玄関ポーチ南壁は役場職員が鴨川市太海(ふとみ)海岸で採取した蛇紋岩を積み上げたもので、城壁の狭間(さま)をイメージして小窓が開けられている。ポーチの長い庇に浮かび上がる曲線は、夷隅川を表す。大多喜城が舞鶴城(ぶかくじょう)と呼ばれたことから、屋上のオブジェ、大会議室のドアの引き手や天井の梁の彩色などに鶴の造形や絵柄が多数あしらわれ、歴代大多喜城主ゆかりの蝶や扇の図柄も装飾のモチーフとされている。当時日本では無名だったスペインの建築家ガウディに影響を受けた今井氏は、屋上のペントハウスの天上と東西の壁、1階への採光窓をモザイク画で飾り、「大多喜町の人々の幸ある生活の祈りであるように」と願いを込めた。

大会議室扉引手「双鶴」
ボランティアガイドの山近さんは、「1957年に世界初の人工衛星が打ち上げられたこともあり、地下階段の壁面には太陽や月と並んで人工衛星が描かれています。モザイク画も宇宙を題材に趣向が凝らされているところに壮大さを感じます」と説明する。
平成24年、老朽化で一時解体の計画のあった中庁舎は、保全を求める多くの声を受け再生工事が行われた。当時の姿を可能な限り維持しながらコンクリートの補修、耐震補強工事が進められ、細かな工芸美術は丁寧に修復された。それに先立ち新築された本庁舎は町内に今も残る町屋から発想を得た建築で、黒を基調とした趣深いたたずまいだ。

屋上のモザイク画
一連の設計は公募により千葉学建築計画事務所が担当し、この官民協同の保全事業が評価され、『ユネスコアジア太平洋文化遺産保全賞』を受賞。その他多数の賞を受賞し、20世紀日本建築の保存再生事例として注目されている。
庁舎内は平日に限り予約により見学できる。問合せは大多喜町総務課へ。ボランティアガイド希望の方は観光協会まで(城下町散策との組合せ可能)。
問合せ:
・大多喜町総務課 Tel.0470・82・2111
・大多喜町観光協会(観光本陣) Tel.0470・80・1146