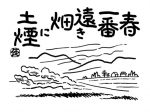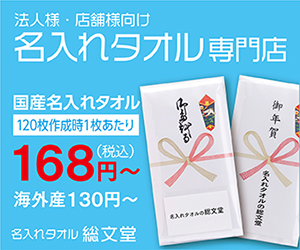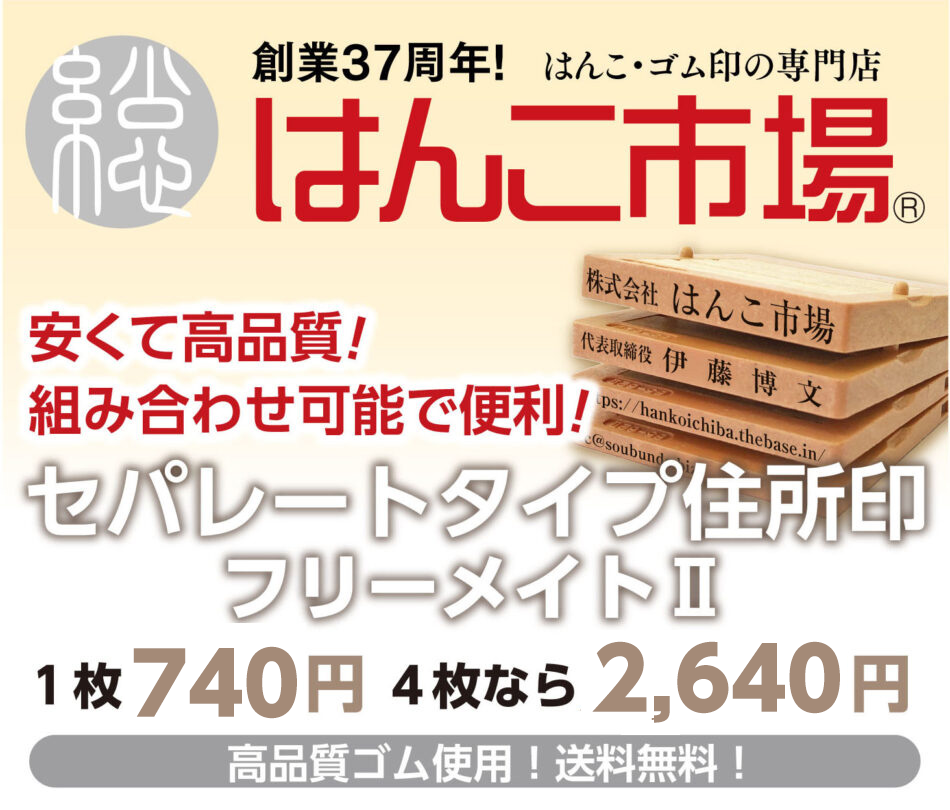古代から伝わる地名
- 2013/11/15
- 市原版

古代から伝わる地名
ちはら台コミュニティセンターで月1回『ちはら台学歴史講座』が開かれている。10月12日の特別講座は『房総の国造(くにのみやつこ)―上海上(かみつうなかみ)と菊間(くくま)国造を中心にして』。前早稲田大学講師佐々木虔一さん(佐倉市在住)が80人の聴衆を前に東アジア、日本、地域の史料を読み解き古代の国府があった市原の歴史を講義した。
紀元前1世紀の日本にはすでに100余りの国があったと中国の史料に残る。『国造』とは6世紀から7世紀ごろに大和政権から統治権を認められた各地域の首長のこと。上総には養老川流域の上海上(かみつうなかみ)、村田川流域の菊麻(ククマ)など6つの勢力があった。佐々木さんは「ククマの『クク』は閉じられた場所や海沿いに生えるカヤツリ草の一種という意味もあった。狭いが海産物や作物の豊かな地で、麻も採れたのかもしれない」と推理。
房総の古墳と国造の分布図を示し「時代が一致しない遺跡もある。両者の関係を研究したらおもしろいのでは」と聴衆を考古学の世界に誘う。奈良時代に菊麻は市原郡となる。律令制になっても国造名を引き継ぐ郡が多いのになぜ市原になったのかは謎。10世紀に編纂された史料には市原郡には濕津(うるひつ)(潤井戸)、菊麻(菊間)、海上郡には山田、鳴穴などの郷名が残る。「鳴穴とは嶋穴(しまあな)だろう」とのこと。
参加した地元出身の女性は「慣れ親しんだ地名に古い由来があると知った」と興味を持った様子。房総古代学研究会の男性は「地名は歴史の痕跡。後世に残してほしい」と思いを語った。