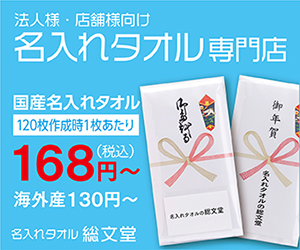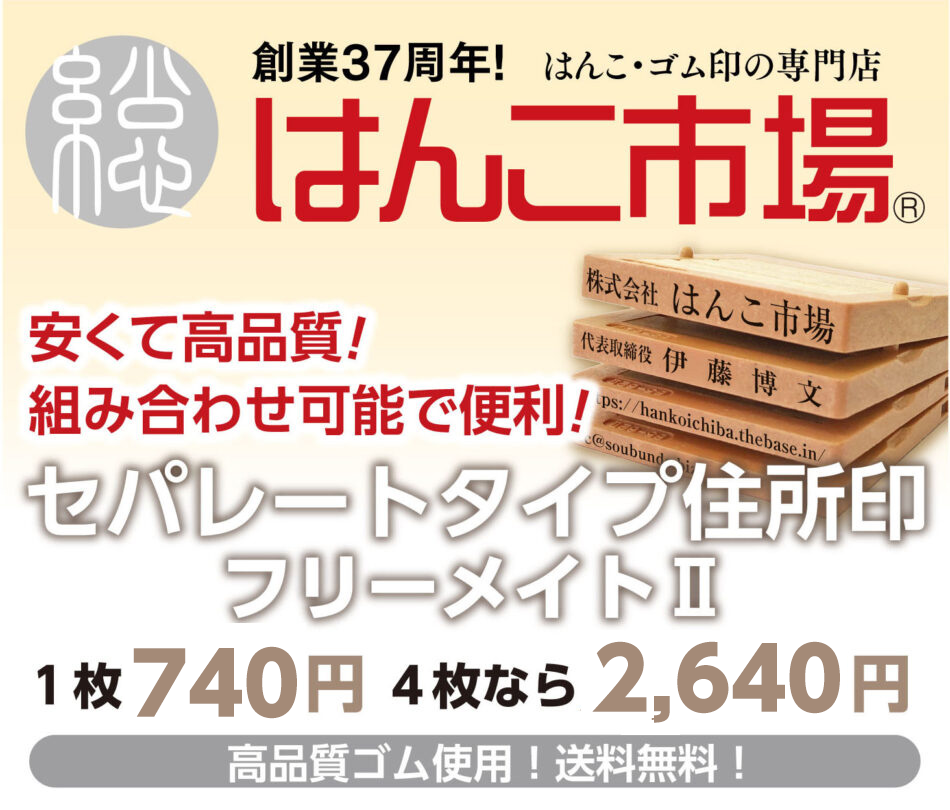- Home
- 市原版, シティライフ掲載記事
- 根性ケヤキが見守る 龍性院(りゅうしょういん)大改修
根性ケヤキが見守る 龍性院(りゅうしょういん)大改修
- 2016/2/5
- 市原版, シティライフ掲載記事

中世の古文書に勝馬郷と記述が残る市原市勝間。古くから地域の信仰の支えとなってきた新義真言宗龍性院吉祥寺がある。真言宗高野山の開創1200年にあたる平成27年、11月28日に落慶法要が厳粛に行われた。
江戸後期に再建されたと伝わる龍性院は、定期的に補修してきたものの数年前から傷みが目立ちはじめた。トタン屋根はめくれ雨がしみ込み、外壁の塗装もはげ危機的状態。檀家でもある住民たちの「次世代に引き継ぎたい」との強い思いがあっても、高額な改修費に公的な補助金など出る当てはなかった。そこで住民たちは何度も話し合い、平成26年秋、ついに自分たちの浄財で「平成の大改修」を決意した。
新たな本堂は半恒久的に使える銅板の屋根と卍模様の鬼瓦、外壁の取り付け、耐震工事など土台から補修がほどこされた。境内も入口の急峻な外階段を御影石にし、崩れそうな斜面上にあった30体近い石造物を移動した。
また、改修により、本堂にあった四国八十八カ所三番札所金泉寺の番札は天明3年(1783)弓削田仁右衛門奉納と判明した。子孫にあたる檀家総代の弓削田喜行さん(67)は「祖先に会えた気がした」と感激し、新たに石塔を建立したという。
 龍性院の総本山は和歌山県の根来寺、住職は荻作にある満光院の淳道さんが兼務する。郷土史家で檀家筆頭総代の佐野彪さん(76)によると起源は定かではないが「文禄3年(1594)の検地帳にのちの龍性院と考えられる歓行院の名がある」とのこと。天明2年(1782)の墨書があるご本尊の不動明王は昭和40年代に一度盗まれ、戻ってきた経緯があるそうだ。
龍性院の総本山は和歌山県の根来寺、住職は荻作にある満光院の淳道さんが兼務する。郷土史家で檀家筆頭総代の佐野彪さん(76)によると起源は定かではないが「文禄3年(1594)の検地帳にのちの龍性院と考えられる歓行院の名がある」とのこと。天明2年(1782)の墨書があるご本尊の不動明王は昭和40年代に一度盗まれ、戻ってきた経緯があるそうだ。
昭和19年には東京柳橋から約30人が龍性院に学童疎開してきた。ところが昭和20年3月、児童が東京に戻った直後に東京大空襲があった。弓削田さんによると「その後、家に宿泊した2人からの音信はなかったと聞いている」という。
大きな宝篋印塔が目を引く境内にはかつて滑り台や鉄棒があった。戦後、勝間の子どもたちは学校から帰るとドッジボールをし、本堂の卓球台で遊んだ。檀家総代の石井勝吉さん(73)が「けんかしながら大きくなった」と振り返ると茂手木恒(72)、弓削田茂之さん(67)もうなずく。
みごとによみがえった本堂を見上げ、佐野さんは「信仰心が薄くなり、人口も減った」としみじみと語る。しかし、龍性院は今も定期的に男性の太子講や女性が集まる講、町会行事などが開かれ住民をつないでいる。境内入口の両側には大きな桜の切り株がある。近所の人が日露戦争に出征したときに植えたと伝わる樹齢120年以上の木。しかも、ひとつの切り株から住民が「勝間根性ケヤキ」と呼ぶ若木が育っている。