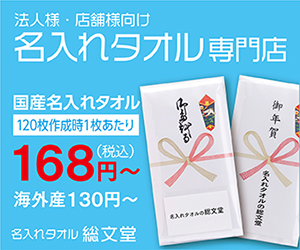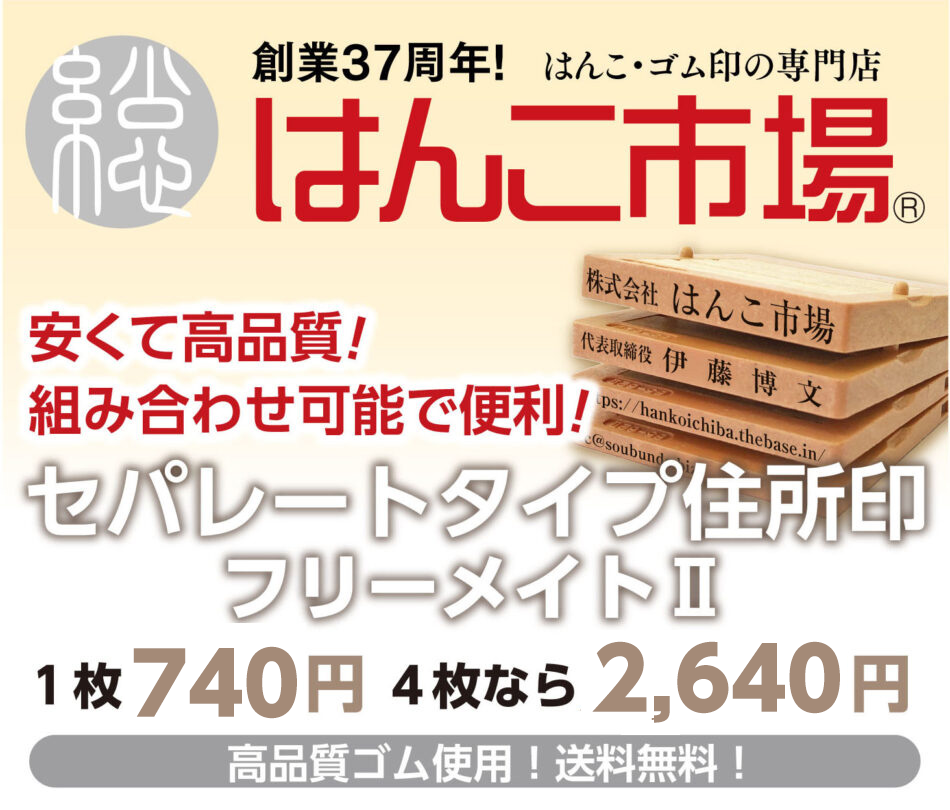- Home
- 市原版, シティライフ掲載記事
- 盆と正月の意外なつながり
盆と正月の意外なつながり
- 2016/7/8
- 市原版, シティライフ掲載記事

日本人には欠かせない行事
 6月5日(日)、三和コミュニティセンター主催の『三和の民俗―盆と正月―』講座に訪れた受講生は12名。講師は日本民俗学会会員で江戸川短期大学名誉教授の鈴木仲秋(ちゅうしゅう)さん。生まれも育ちも新堀の鈴木さんだが、三和地区を含めて周辺地域の慣習の違いに好奇心を覗かせる。「学問的には1カ所だけではなく、各地域を比較してみないと違いは分かりません」と冒頭に説明し、まずは過去から遡って様々な風習の違いを探る。
6月5日(日)、三和コミュニティセンター主催の『三和の民俗―盆と正月―』講座に訪れた受講生は12名。講師は日本民俗学会会員で江戸川短期大学名誉教授の鈴木仲秋(ちゅうしゅう)さん。生まれも育ちも新堀の鈴木さんだが、三和地区を含めて周辺地域の慣習の違いに好奇心を覗かせる。「学問的には1カ所だけではなく、各地域を比較してみないと違いは分かりません」と冒頭に説明し、まずは過去から遡って様々な風習の違いを探る。
今は日に3回の食事を取る日本人だが、中世までは2食だったし、かつては土葬だった埋葬方法も、近年になって火葬へと変化した。たとえ同じ時代を生きていても、すぐ近くに住んでいたとしても違う風習はある。そんな中でも身近なものが、『盆と正月』なのだ。
「みなさんのお宅では、お盆の始まりはいつですか?」と尋ねる鈴木さん。千葉市内などではお盆が7月という地域も珍しくない。だが、三和地区周辺では8月に盆を迎える所がほとんどで、それは7月だと秋風が立たないという気候の問題に由来する。受講者が12から13日に盆が始まると共通して手を挙げたが、迎え方を考えると決して1つではない。「山の上やふもと、家の前や道の辻など様々な場所でお迎えをします。さらには、盆があける時に送っていく場所、時間も違うんです」と鈴木さんが説明する通り、受講者の家でもそれぞれ違っていた。それは正月の雑煮にも共通している。「私の家は鶏肉と里芋を入れます」と話す人もいれば、「小松菜も入れるよ」という人がいる。それは日常の食事など、嫁が入ることにより変化していると考えられるのだとか。
では、そんな2つの行事に共通していることは何か。鈴木さんは、「お墓参りです。地域によっては、正月にお墓にお飾りを置くところもあるんですよ」と話すが、「なぜ盆と呼ぶのか、言葉の意味さえ分かっていないんですよ」と続ける。
また、磯ヶ谷地区に寺が1つも残っていないことに内容が及ぶと、受講者からは「どうして廃仏毀釈運動(はいぶつきしゃくうんどう)が明治初年に起きた時、残った寺と残らなかった寺があるんですか。前から、とても興味があったんです」と質問の声。それに対して、「廃仏毀釈運動は、すべての地域で行われたわけではないと考えられています。どなたか、磯ヶ谷地区で調査されてみてはいかがでしょうか」と鈴木さんがすすめる場面もあった。
また、「民俗学は反省の学問と言われています。民俗とは生活そのものです。日本人としてどうするのか、多方面でよく考える必要がありますね」と鈴木さんは語る。違いを見つけることは面白い。なにより悲しいのは、ずっと続いてきた風習がいつのまにか廃れてしまうことだろう。