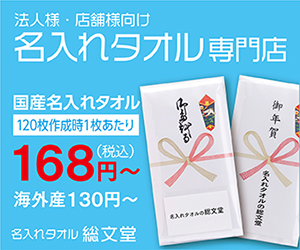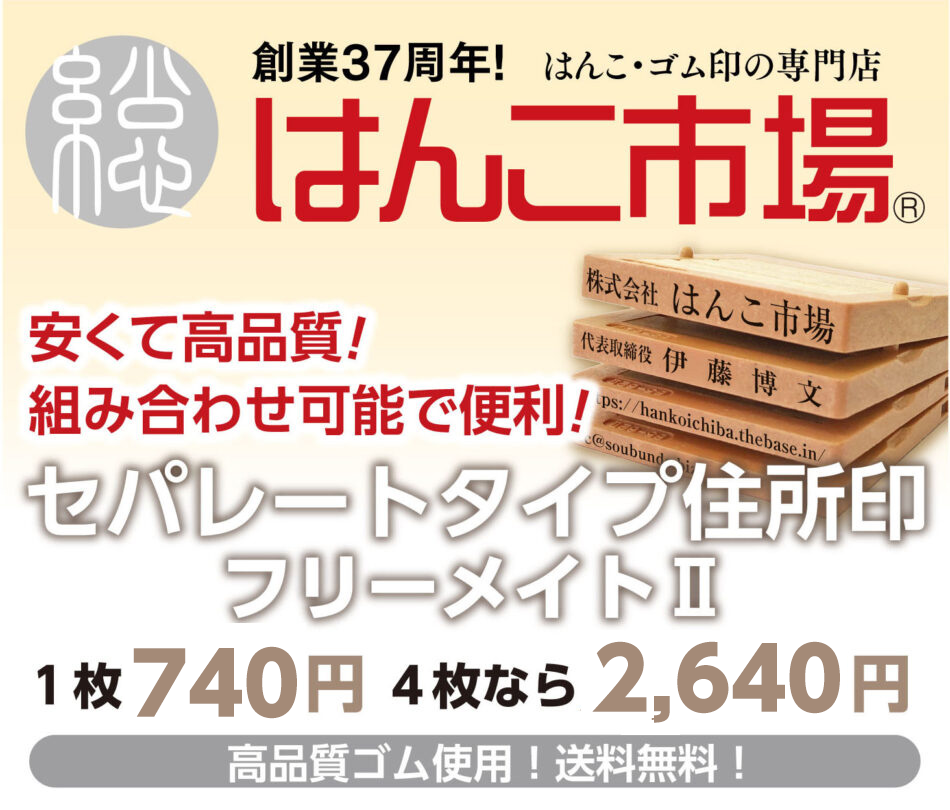- Home
- 市原版, シティライフ掲載記事
- 貴重な習俗 朝粥行と八日講
貴重な習俗 朝粥行と八日講
- 2018/1/1
- 市原版, シティライフ掲載記事

 昨年の11月3日朝6時、市原市北青柳地区に鳴り響いたのは法螺貝、出羽三山信仰の行人が集まる八日講開催の知らせ。北青柳三山行人会代表・火の親の小倉澄夫さんは「朝粥を食べるのではなく、朝食前に行うので朝粥行といいます」と背中に登拝の証である朱印が押された白装束で話す。町の角々で告げ法螺が鳴ると、80代の男性が「昔は毎月あった」と門まで出てきたり、野球のユニフォーム姿の子どもが驚いた様子で窓から覗いたりしていた。
昨年の11月3日朝6時、市原市北青柳地区に鳴り響いたのは法螺貝、出羽三山信仰の行人が集まる八日講開催の知らせ。北青柳三山行人会代表・火の親の小倉澄夫さんは「朝粥を食べるのではなく、朝食前に行うので朝粥行といいます」と背中に登拝の証である朱印が押された白装束で話す。町の角々で告げ法螺が鳴ると、80代の男性が「昔は毎月あった」と門まで出てきたり、野球のユニフォーム姿の子どもが驚いた様子で窓から覗いたりしていた。
朝粥行を終えると、北青柳公民館で数名の地区委員とともに祈りを捧げる。法螺貝で神様を呼び出し、火打石で心にある邪心を浄化、九字を唱え、お線香を供え、御梵天由来、御山縁起、「懺悔懺悔六根罪消」と湯殿山御祝詞を読み上げた。
その後、梵天を持ち、再び法螺貝を吹き鳴らしながら特別工業地区内を通り、市原緑地運動公園内の共同墓地にある三山供養塚で酒、水、米、塩を供え、仏の祈りを捧げる。祈りは西青柳の火の親、80代の山下貞蔵さんが所持する大正7年の経典が元だそうだ。若宮八幡神社境内の記念塚でも同様にお供えをし、神の祈りを唱える。「神と仏の祈りなのは神仏習合の名残り」だそうだ。
貴重な習俗を残したいと講を取り仕切る小倉さん。「かつては毎月8日と20日に集まり、梵天づくりや拝みを行いました。今は年に一度です」と嘆く。東京から駆け付けた三山信仰の研究者、羽黒山荒澤寺派の女山伏、本田晶子さんも「貴重な体験です。他には残っていません」と白装束で回っていた。