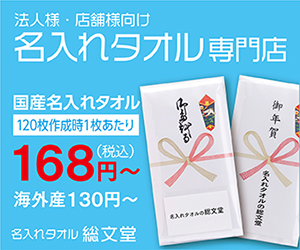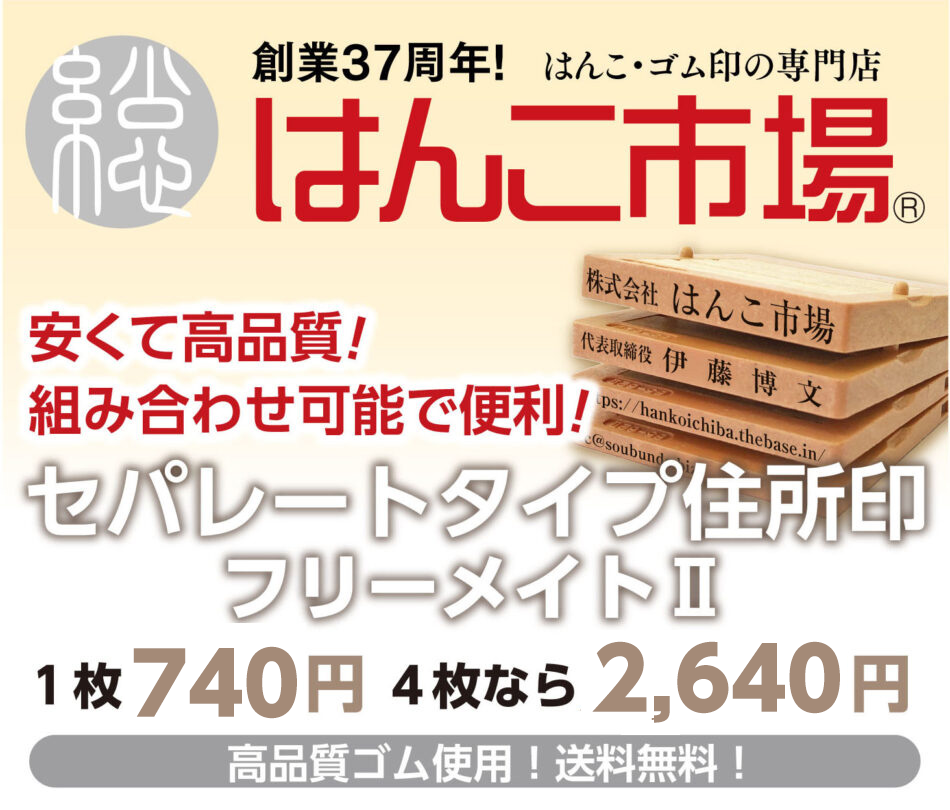稲荷台一号噴出土
- 2013/8/2
- 市原版

稲荷台一号噴出土
「『王賜』銘鉄剣」の謎に迫る
昭和52年に市原市の稲荷台一号噴で鋲留短甲(鉄の鎧)、鉄鏃(矢じり)、刀子(小刀)と共に鉄剣が発掘された。鉄剣は、発掘当初は欠失部分があり、錆もひどく文字は見えなかったが、昭和62年に国立歴史民俗博物館(佐倉市)で行われたエックス線撮影の結果、金銀合金を埋め込んだ文字の彫跡が浮かび上がり、日本最古の文字資料として反響をよんだ。
市内在住、共立女子短期大学の前之園亮一教授は「自分が始めるしかない」と、先行研究がないために解明するのが困難な5世紀中葉の歴史を読み解き、銘文入りの鉄剣について20年以上にもわたる研究を重ねて研究書を出版し、自説を打ち出した。
同鉄剣の表には「王賜□□敬□(安)」、裏には「此廷□(刀)□□」とあり、推定十二文字が記されている。そのうち判読できるのはわずか6文字(カッコ内は推定)だが、王からの賜り物、朝廷の刀であると解読。では、この「王」とはいったい誰のことなのか。古墳の年代が五世紀中葉(441年から460年)頃であること、信憑性の高い中国の歴史書『宋書』によると允恭天皇と同一人物である倭王済の在位期間が443年から461年であることから、「王」とは允恭天皇のことであると推定、更に、剣は同古墳の被葬者である市原の中小豪族「刑部」に下賜されたものであるとした。
全国的に広がっていた「オサカベ」と名乗る集団の起源・元本は、允恭天皇の皇后である忍坂大中姫に仕えて山間部で猪養をし、入墨を習俗とした「オシサカベ(忍坂部)」であり、「刑」という漢字には「入墨」という意味があることなどから「刑部」と表記したと考えられる。刑部は忍坂宮に猪の肉や猪の油すなわち猪膏を献上していた人々であるという。「王」が一号噴の被葬者に鉄剣を贈ったのは刑部として長年仕えたことへの褒美、高句麗遠征に従軍した刑部への褒美、あるいは忍坂(現在の奈良県)の武器庫に勤務したからである。武器庫では、刑部が猪膏で武器武具を磨く役割を担っていたという。
「五世紀は、当時書かれた信頼できる記録が皆無に近い。その中で、稲荷台一号噴の十二文字は大変貴重です」と教授。今年2月に『「王賜」銘鉄剣と五世紀の日本』(岩田書院刊)を出版、9月15日(日)にはサンプラザ市原で「『王賜』銘鉄剣から見る市原の豪族の活躍」と題した講演会を行う。また、毎月第1土曜日にサンプラザ市原で活動中のサークル『こしば古代史の会』の講師も努めている。尚、「『王賜』銘鉄剣」のレプリカが市原市埋蔵文化財調査センターで展示されている。(礒川)