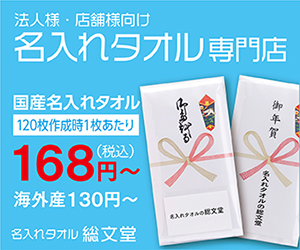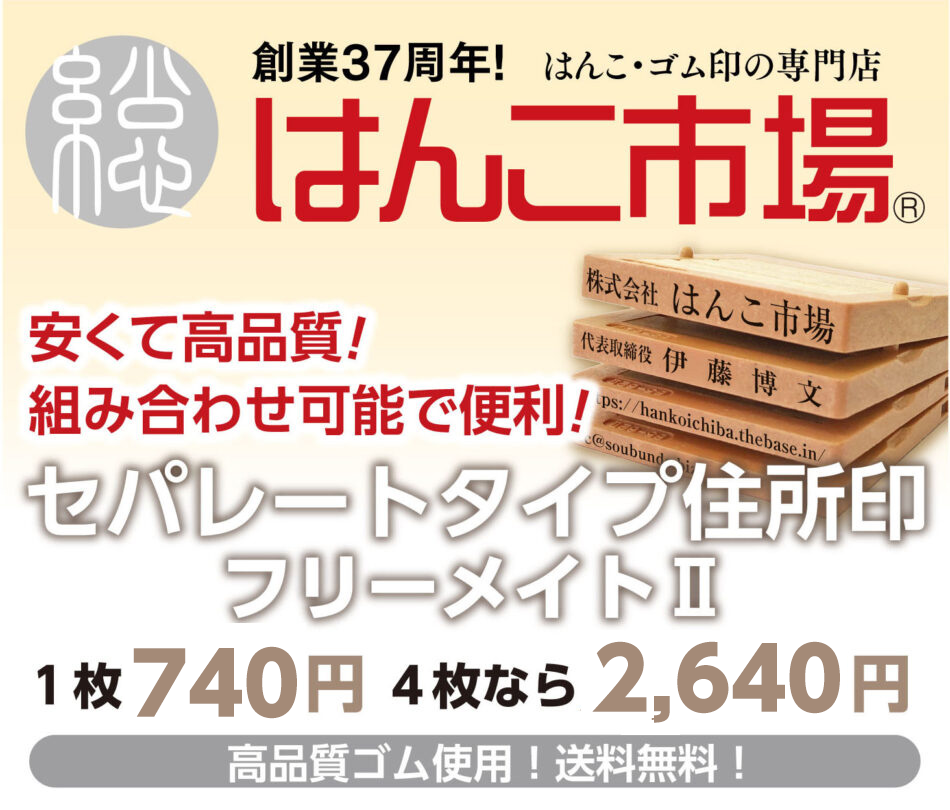- Home
- 市原版, シティライフ掲載記事
- 地域のつながりが防災の鍵
地域のつながりが防災の鍵
- 2015/6/26
- 市原版, シティライフ掲載記事

火災や自然災害が発生した時、活躍する消防団。普段から地域と関わりが深く、いざという時には頼もしい存在だ。しかし『自らの地域は自らで守る』という意識が希薄となった現在、団員は減少。市民有志の『地域防災を考える会』は4月中旬、タウンミーティングを1日2回開催し、消防団OB、消防団員、一般市民などを交え、率直な意見交換を行った。
消防団は、救護や消火、避難誘導の各訓練、火災予防の呼びかけなどを普段から行っている。特別職地方公務員で、年間活動に対し、自治体から謝礼程度で手当てが出る。近年はサラリーマンの団員が増加、現場に来られず、仕事との両立が難しい、などの課題がある。多くの市民が消防団の意義や地域での役割をよく知らず、敬遠されるため団員補充も難しいという。「消防団は火災現場に一番早く到着することも多い。交通整理など消防の支援活動をし、消火が終わり消防局と警察が撤収しても、火種の見張りや探索などをする。夜中から朝までという現場もあり、重要性をもっと知って欲しい」と現役消防団員。
町会で行う自主防災などでも、地域での人のつながりがきちんと機能しなければ、独居老人・在留外国人・障害者などの情報弱者の迅速な避難も難しく、実際に災害が起こった時に被害が増えるのでは、という危惧も出た。主宰者のひとり、大矢仁さんは、「地域のつながりが大事、という認識は皆が持っています。しかし、それを実際の防災活動に結びつけ、多くの市民に意識して参加してもらうことが、一番難しいようですね」と話した。