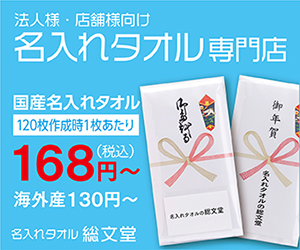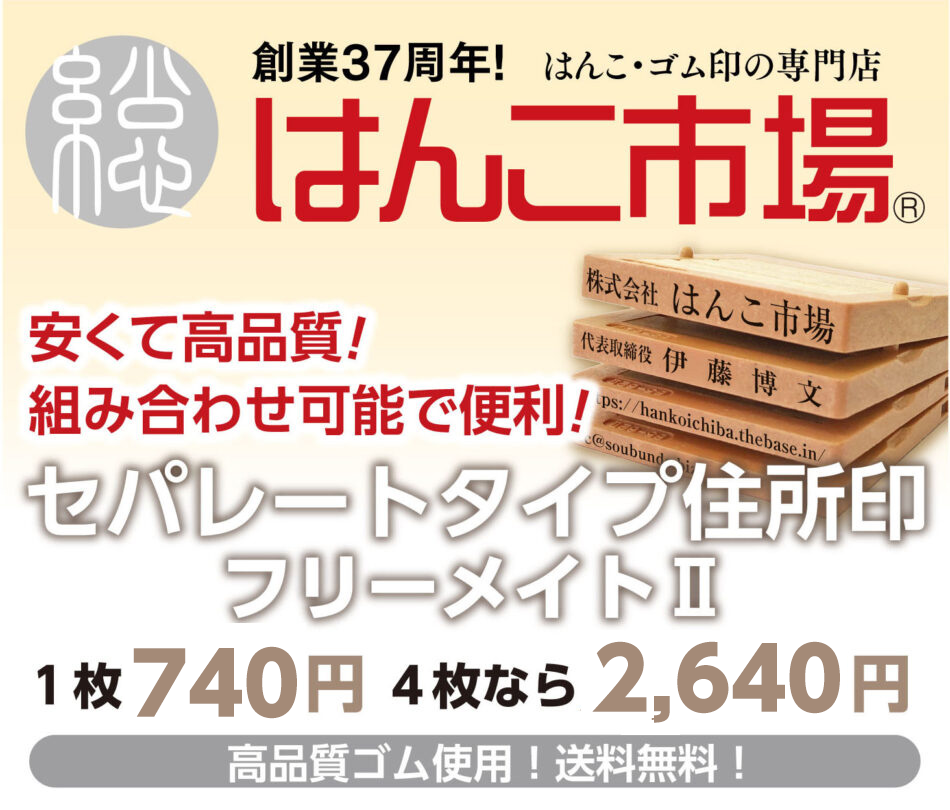- Home
- 市原版, シティライフ掲載記事
- 私たちは他の生き物と関わりあいながら、生きている
私たちは他の生き物と関わりあいながら、生きている
- 2016/6/10
- 市原版, シティライフ掲載記事

国分寺公民館で主催講座『市原自然探検隊』(全3回、バス研修含)が開かれ25名が参加した。第1回目の5月17日は講義で、第1部は『市原市の生物多様性について』と題し、市原市環境部の高橋眞澄さんが生物多様性への市の取り組みについて述べた。生物多様性とは生き物同士のつながりのこと。農作物や家畜を食料とし、綿や麻の衣服を着て、木で家を建てる人間もその生き物の一員であり、他の生き物と結びついて生きている。ところが近年、人間がもたらす自然への様々な影響、さらには地球温暖化などが、本来の生態系を破壊し、多くの生き物たちを危機的状況に陥らせている。そこで、将来の子どもたちに生物多様性の恵みを享受し、自然と共生する社会を残すため、平成26年度から『(仮称)市原市生物多様性地域戦略』の策定に取り組み、市民が参加するワークショップ開催などの活動を行ってきた。今後は同戦略をまとめあげ、市民からの意見募集(パブリックコメント)も行うので興味のある方は広報などを要チェック。
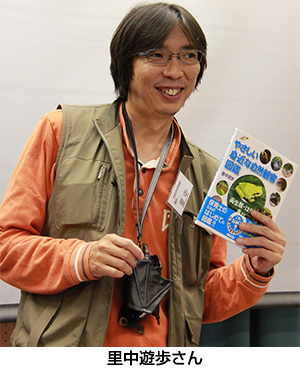 第2部は日本野生生物リサーチセンター代表の里中遊歩(ゆうほ)さんによる『里山に生息する生き物たち』。県内で見られる両生類、爬虫類、野鳥を中心に、見やすい写真とイラスト、わかりやすい言葉で生き物の特徴や見分け方について紹介した。冒頭で「千葉県で見られない生き物は?」とのクイズを出した。正解はトノサマガエル。「え、そうなの?」と驚く参加者。「みんながトノサマガエルだと思っているのは、実はトウキョウダルマガエル。似ているけれど、背中がボコボコしているのがトノサマガエル、ブツブツしているのがトウキョウダルマガエル。よく見てみて」と里中さん。トノサマガエルは関東平野には生息していない。
第2部は日本野生生物リサーチセンター代表の里中遊歩(ゆうほ)さんによる『里山に生息する生き物たち』。県内で見られる両生類、爬虫類、野鳥を中心に、見やすい写真とイラスト、わかりやすい言葉で生き物の特徴や見分け方について紹介した。冒頭で「千葉県で見られない生き物は?」とのクイズを出した。正解はトノサマガエル。「え、そうなの?」と驚く参加者。「みんながトノサマガエルだと思っているのは、実はトウキョウダルマガエル。似ているけれど、背中がボコボコしているのがトノサマガエル、ブツブツしているのがトウキョウダルマガエル。よく見てみて」と里中さん。トノサマガエルは関東平野には生息していない。
水田で鳴き声を聞くことの多いウシガエルは外来種。戦前に食用としてアメリカから輸入されたものの需要がなく野に放たれたものが繁殖した。ほかにもアメリカザリガニやミシシッピアカミミガメ(通称ミドリガメ)など多くの外来種が国内で生息している。「外来種の中には国内の生態系を乱すものもあり、害獣と呼ばれることがある。だが、外来種を海外から連れてきたのは人間。害があるからと駆除するだけでなく、原因を作った人的行為への反省が大切」と呼びかけた。
「生き物についての知識がたくさん得られて楽しい」と参加者。講義で生き物の観察ポイントを聞いたあとは、ゴミをあさるからと嫌われているハシブトカラスにさえも愛着がわく。人間だけが特別な生き物ではない。同じ土地に生きる他の生物とのつながりについて、改めて考えてみたいものだ。