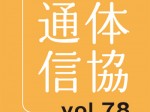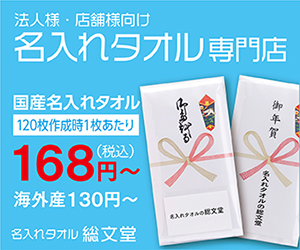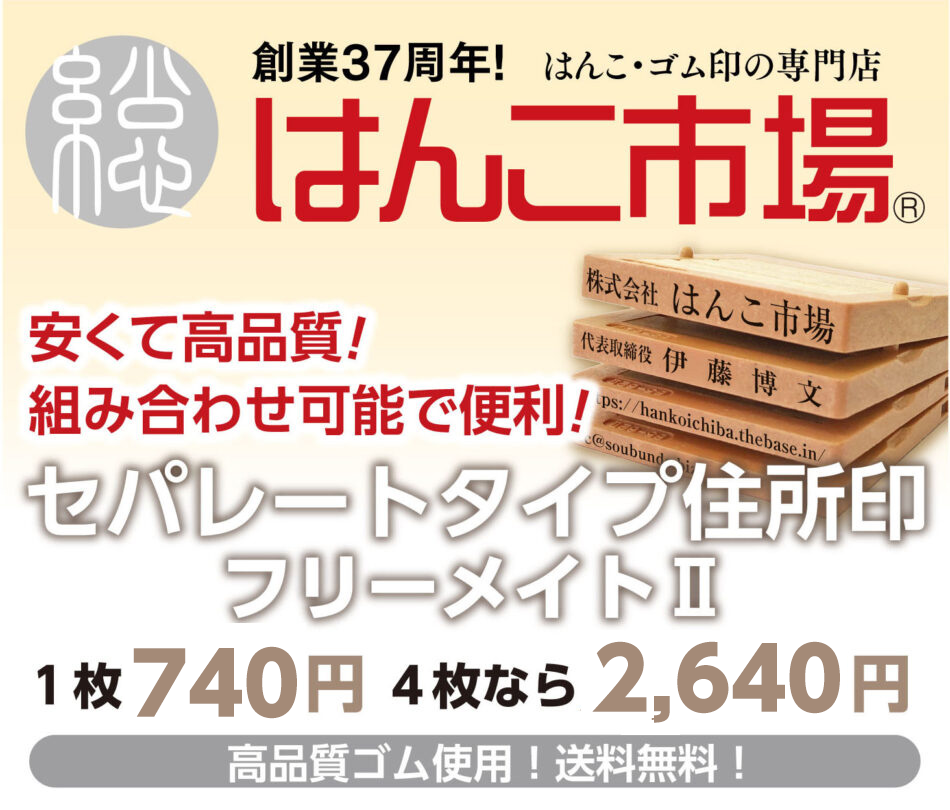- Home
- 外房版, 市原版, シティライフ掲載記事
- じわじわ来ているぞ!中東出身、謎のスイカ現る
じわじわ来ているぞ!中東出身、謎のスイカ現る
- 2017/1/27
- 外房版, 市原版, シティライフ掲載記事

 市原市松崎在住の福原崇さん(67)は、昨年自宅の畑で収穫されたスイカを手に笑顔を浮かべた。大きな緑色のそれは枕のような形をしていて、一見冬瓜のようだ。しかし、切ってみれば大違い。中は綺麗な赤く熟れたスイカなのだ。「このスイカを栽培し始めてから、もう20年近く経ちました。面白い話ですが、ある飛行機のパイロットが中東に仕事で行き、そこで手に入れた種をもらうことができたのが、栽培のきっかけです」と話す福原さんだが、どうやら中東の『ヘンダワナスイカ』だろうということだけで、実際にどの国のものかはっきりしていないという。
市原市松崎在住の福原崇さん(67)は、昨年自宅の畑で収穫されたスイカを手に笑顔を浮かべた。大きな緑色のそれは枕のような形をしていて、一見冬瓜のようだ。しかし、切ってみれば大違い。中は綺麗な赤く熟れたスイカなのだ。「このスイカを栽培し始めてから、もう20年近く経ちました。面白い話ですが、ある飛行機のパイロットが中東に仕事で行き、そこで手に入れた種をもらうことができたのが、栽培のきっかけです」と話す福原さんだが、どうやら中東の『ヘンダワナスイカ』だろうということだけで、実際にどの国のものかはっきりしていないという。
だが、食べてみればさらに驚きだ。糖度を計れば14度と異常な甘さ、頬や地面に滴り落ちるほどの水分量、そして見事なシャキシャキとした歯ごたえ。そして、「糖度が14度を超すためには、気温や天候に左右されるのでビニールをかけてトンネルにしたり、ほんの少しだけ農薬を使うなど工夫が必要です。また、蔓にできる15枚目から25枚目の葉の間に出来る実が一番美味しいので、他は早目に摘んでしまうことも必要です」と育てるコツを語る。
昨年は200個もの収穫に成功、やはり一番嬉しいのは手にした人の喜ぶ顔だ。中東で育つ作物ゆえに、初めは日本の気候が合わなかったのか蔓がのびてもポキポキ折れてしまった。だが、次第に丈夫になり、実も大きくなった。市原商工会議所の浅賀恒さんは、「最大26㎏になったこともあります。以前、このスイカに似ている北海道の『ゴジラの卵』というのを見つけて取り寄せてみたんですが、やはり違いましたね。これから、三和のブランドとして長い目で盛り上げていけたらと望んでいます」と話す。縦横の比率を均等にして形を揃える、種を植える時期をずらして収穫の間隔を長くすることなどが課題だ。また、三和地区の名産として確実な品質を保つために糖度の基準を設け、その高さを超えたスイカにだけ専用のシールを貼って市場に出すなどの試みを考えている。
「かつては中東の人の食を支えたスイカが、イランでは今内紛が続いて農業どころではなく、種もないようです。それが海を越えて日本で栽培されているなんて不思議ですね」と福原さんは想いを馳せる。
また、スイカだけでなく桃や山ワサビなども育てる福原さんの特技は蕎麦打ちだ。福島県を産地とするそば粉で、こちらも20年ほど打ち込み、今では毎月2回三和コミュニティセンターで蕎麦教室を開催している。「生徒さんは30人ほどですが、みなさんかなり上達されています。いつでも参加可能です」という福原さんに、「年越し蕎麦を自分で作りたかったけれど綺麗なのができず、ここで教えてもらって2年半、家族も喜んでくれるようになりました」と生徒の1人も続けた。日本国内関わらず、1つの食材、1つの料理が人間の心をほっと和ませるのは、いつの時代も決して変わることがないのだろう。