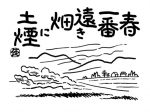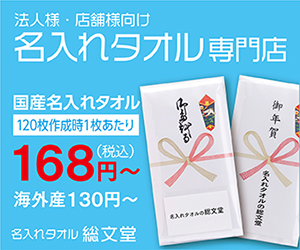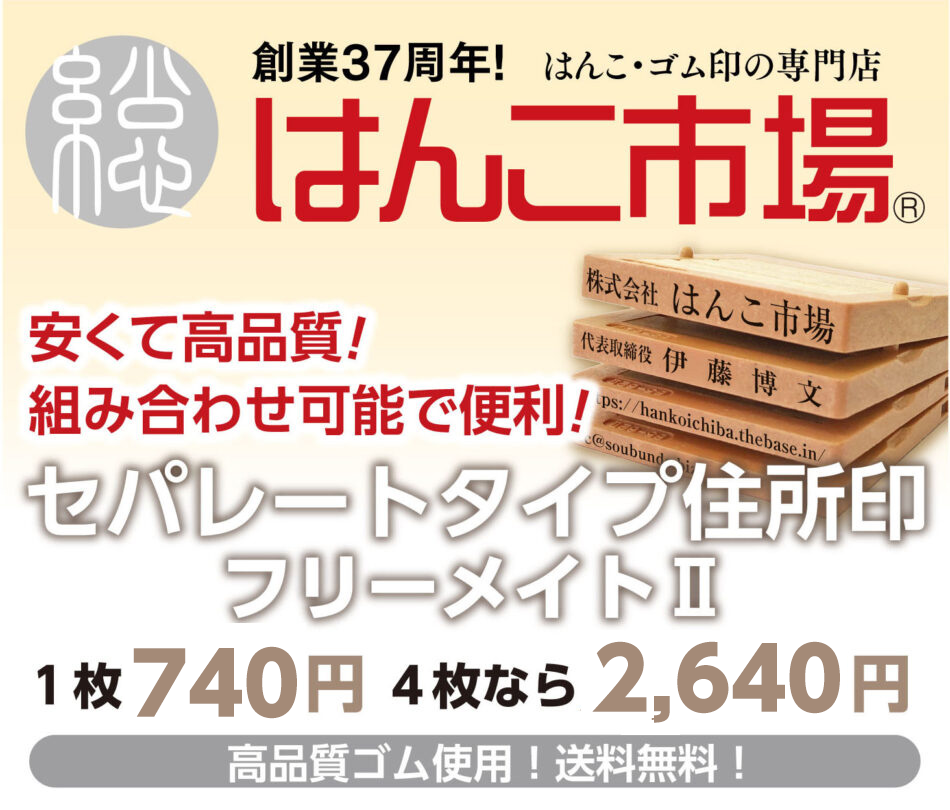- Home
- 市原版, シティライフ掲載記事
- お正月を彩る絣の犬
お正月を彩る絣の犬
- 2018/1/1
- 市原版, シティライフ掲載記事

図案に従って予め部分的に染めておいた糸で織る絣。糸の特長のため作り手がどんなに丁寧に織っても、模様はかすれて見える。発祥は古くインドらしいが、江戸後期に久留米、備後、伊予など各地で織られるようになり、明治以降庶民の衣服として最盛期を迎えた。いくつもの工程を経てできた布は素朴な温もりがあり、今も手に取る人を惹きつける。
 昨年12月から開催された茂原市本納公民館主催講座『絣で作る干支の犬』(全4回)。初日に紺絣のかわいい犬を作った参加者13名は、取材日、木綿でできた縞模様の風呂敷を切り分けた布で色違いの犬を縫っていた。
昨年12月から開催された茂原市本納公民館主催講座『絣で作る干支の犬』(全4回)。初日に紺絣のかわいい犬を作った参加者13名は、取材日、木綿でできた縞模様の風呂敷を切り分けた布で色違いの犬を縫っていた。
まず、布に型紙で印をつける。頭2枚、胴体の腹部分1枚と背の部分が2枚、尻尾2枚を切るのだが、型紙の置き方で柄に変化が出るので、1枚の風呂敷から一人ひとり違う犬ができる。柄をどこに入れるかが思案のしどころ。中表に縫い合わせ、表に返し、ふんわりと綿を入れ、顔をつけたら完成する。
参加者たちは「完成するのが楽しみ」、「玄関に飾りたい」とおしゃべりをしながら熱心に手を動かす。60歳を過ぎて裁縫を始めたという女性も「ストレスを忘れ集中できます」と楽しそうに縫う。趣味が高じて人に教えるようになったという講師は気さくで親しみやすい。糸通しが面倒と糸を長くして縫う初心者に「糸は肘の2倍の長さで十分ですよ」と優しく手を貸していた。
公民館の担当者は「作る楽しみ、飾る楽しみ、家族や友人に見せる楽しみを味わってほしいですね」と笑顔で話した。